こんにちは、くりはら けんです。
今回の記事は、クジラボでのキャリアカウンセリング第3回セッションの記録です。
DAY1では「働き方に対するモヤモヤの言語化」、DAY2では「自分が大切にしたい価値観の整理」に取り組んできました。
そしてDAY3のテーマはーー
「働く中で価値を発揮できる『才能・強み』について理解を深める」ことです。
(DAY2までの記録をまだ読んでいない方は↓からどうぞ!)
本編に入る前に、改めて私くりはらの自己紹介です。
- 公立高校の数学教員
- 講師経験を含め、高校で10年以上勤務
- 妻と息子2人との4人家族
前回の宿題:クリフトンストレングスの受検
DAY2終了後の宿題として出されたのは、クリフトンストレングス(ストレングスファインダー)の受検。
自分でも気づいている、あるいは無意識だった「強み」に光を当てていく作業です。
実際に受けてみると、
- 「やっぱり、そうだよね」と納得できるもの
- 「えっ、これが?」と意外なもの
がありました。
今回は、その上位資質をメンターさんとともに深堀りしていった記録です。
上位資質①:調和性
一番上に出てきたのは「調和性」。これは納得でした。
私は人との衝突や、場の空気が悪くなることを強く避ける傾向があります。
中立的な立場で、意見の対立があればそれぞれを理解しようと努める。
そういった行動を、無意識のうちに自然ととっていたことに改めて気づきました。
一方で、「自分の意見や主張を通すことが苦手」という側面もあります。
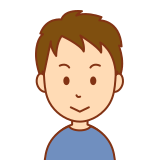
「調和性」が一番に来ている背景には、どんな経験や想いがありますか?

自己主張よりも、周りの声を聞いて理解することの方が自然だった気がします。
対立する意見をどちらも理解できてしまう。結果、いつも”中立的な立場”になってきたように思います。
そのせいか、「自分の意見がない」と感じることも多かった。
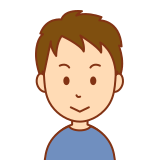
自分の意見を言えるようになりたいと思いますか?

…正直、どちらとも言えないかなと。
円滑な人間関係で穏やかに過ごしたいという気持ちが根底にある一方で、
自分の意見がないことで、”芯”がなくなり、自分のキャリアの軸を見失っているかもしれません。
リーダーとしての在り方:私のタイプとは?
前任校で教務部長を任されたことがあります。
その前任者は、「学校を変えたい!」「自分が理想とする学校に!」という強い思いを持ってましたが、
私はというと、そのような強いリーダーシップを発揮しようとは思っていませんでした。
「学校を変えていく!」という思いは、正直なかったんです。
教務部長として、与えられた役割をこなすことで手一杯。
でもその中でも、他の先生方の意見を丁寧に汲み取り、バランスを取ることには意識を向けていました。
「カリスマ型で引っ張る」のではなく、
「それぞれの個性が発揮される場を整える」タイプ。
自分はそんなリーダーシップのスタイルなのだと気づきました。
学生時代の立場や役割から見えること
中学〜大学にかけて、リーダー的なポジションにつくことが多かった私。
自分から手を挙げたこともあれば、周囲から「やってほしい」と声をかけられたこともあります。
ただ、「みんなを引っ張る」ことには正直なところ抵抗がありました。
では、なぜ任されてきたのか?
”フォロー役”としての力が評価されていたのではないかと、今は思っています。
場の空気や意見の衝突に敏感で、それを調整するのが得意だったからこそ、自然と人に頼られていたのかもしれません。
上位資質②:分析思考
二つ目は「分析思考」。
物事の因果関係や理由を明らかにしたい。
状況に影響を与える要素を整理・把握したい。
そんな思考のクセがあります。
私は数字を扱うことに苦手意識がなく、むしろ好きです。
たとえば、野球観戦が好きなのですが、
- ひいきチームの勝敗データをチェック
- 打率や防御率を見て選手の調子を分析
- 優勝に必要な勝ち数をシミュレーション
といったことを、つい無意識にやってしまいます(笑)
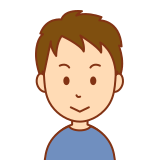
右脳的なアプローチと左脳的なアプローチを組み合わせて考えてみると、くりはらさんの強みが活きやすいかもしれませんね。
「データ分析」「アナリティクス」「定量的〜」というキーワードが、キャリアのヒントになりそうですと教えていただきました。
上位資質③:学習欲
三つ目は「学習欲」。
- 新しい知識を得たい
- 自分を常にアップデートしたい
- 経験や対話からも学びたい
そんな思いが自分の中にあります。
現状維持や、変化のない環境はあまり好きではありません。
そんな環境に身を置くこと、モヤモヤを感じる原因になっている可能性もあることに気づきました。
「学びは楽」だと感じる理由
大学卒業後、通信制大学に通って数学の教員免許を取得。
最近では、FPや簿記といった資格も取りました。
どれも”やらなければいけない”ものではありません。
「学ぶこと」は苦ではない。むしろ”楽しい”んです。
なぜ楽しいのか?
それは、学びには明確な”レール”があるから。
「これを理解すれば資格が取れる」という明快さが、性に合っているのかもしれません。
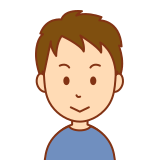
学ぶ原動力って、どこから来ていると思いますか?

いまの原動力は、”キャリアの幅を広げたい”という思いです。
教員しか知らない自分、教員しかできないかもしれないという危機感。
その中で、「得意なこと」や「好きなこと」から新しい道を探したい。
たとえば、数字や論理的思考を活かせる分野ーー
簿記、FP、プログラミングなどにも、可能性を感じています。
まとめ:「強み」とは、自分の内側に眠っているもの
今回のセッションを通して、自分でも気づいていなかった「強み」が見えてきました。
- 調和性 → 意見をまとめる力。チームに安心感を与える存在。
- 分析思考 → データや物事を冷静に捉え、構造的に考える力。
- 学習欲 → 常に知識をアップデートし、変化を楽しめる力
これまで「弱み」だと思っていた部分も、見方を変えれば立派な武器になります。
「調和性」は、優柔不断ではなく、場の空気を調整する力。
「分析思考」は、考えすぎではなく、論理的な構造化力。
「学習欲」は、流されるのではなく、継続して学び続ける原動力。
今後のキャリアを考えるうえで、大きなヒントになりました。
次回のテーマ:「教員以外のキャリア選択肢を考えてみる」
DAY4に向けての宿題は、
「教員以外のキャリアの具体的な選択肢を出せるだけ出してみること」
今回までの自己分析を土台に、
外の世界に目を向け、どんなキャリアがあり得るのかを探っていきます。
自分自身でも、ワクワクとドキドキの感情が生まれているのが分かります。
引き続き、自分との対話を深めていきたいと思います。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!
もし「自分も同じような悩みを抱えている…」と思った方がいたら、コメントやSNSで気軽に話しかけてくださいね。
くりはら けんでした!
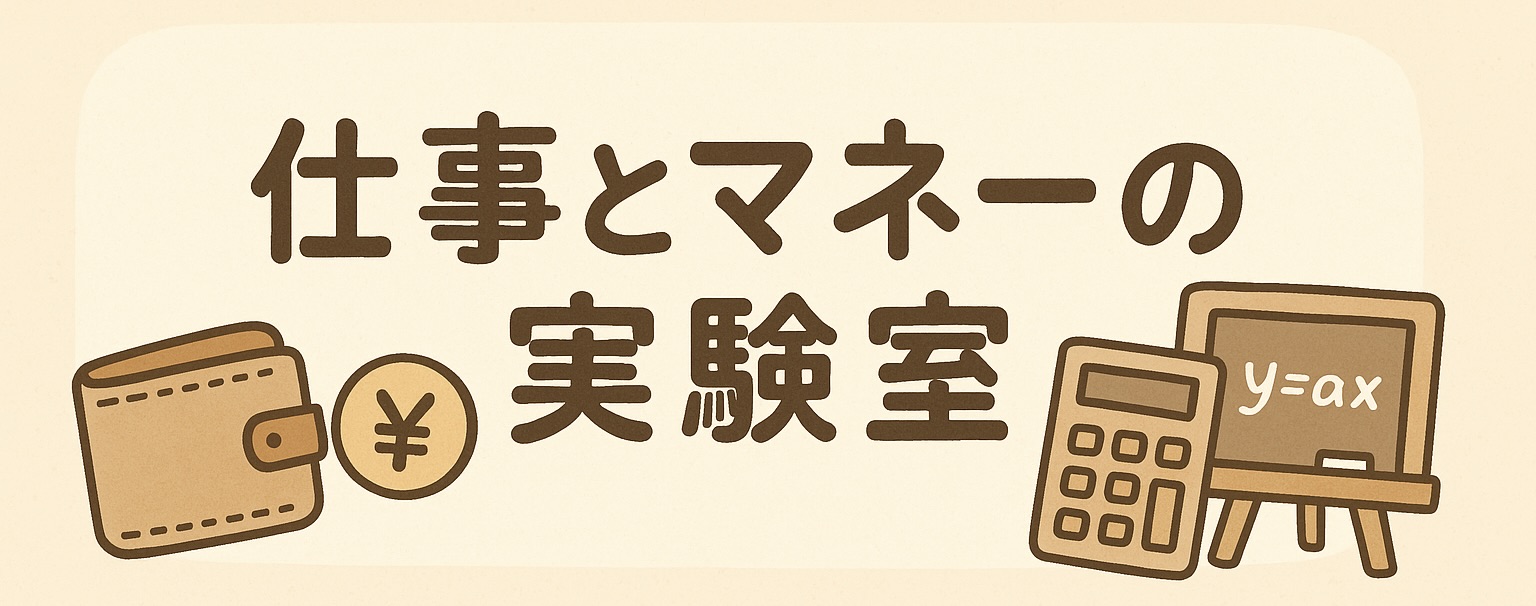
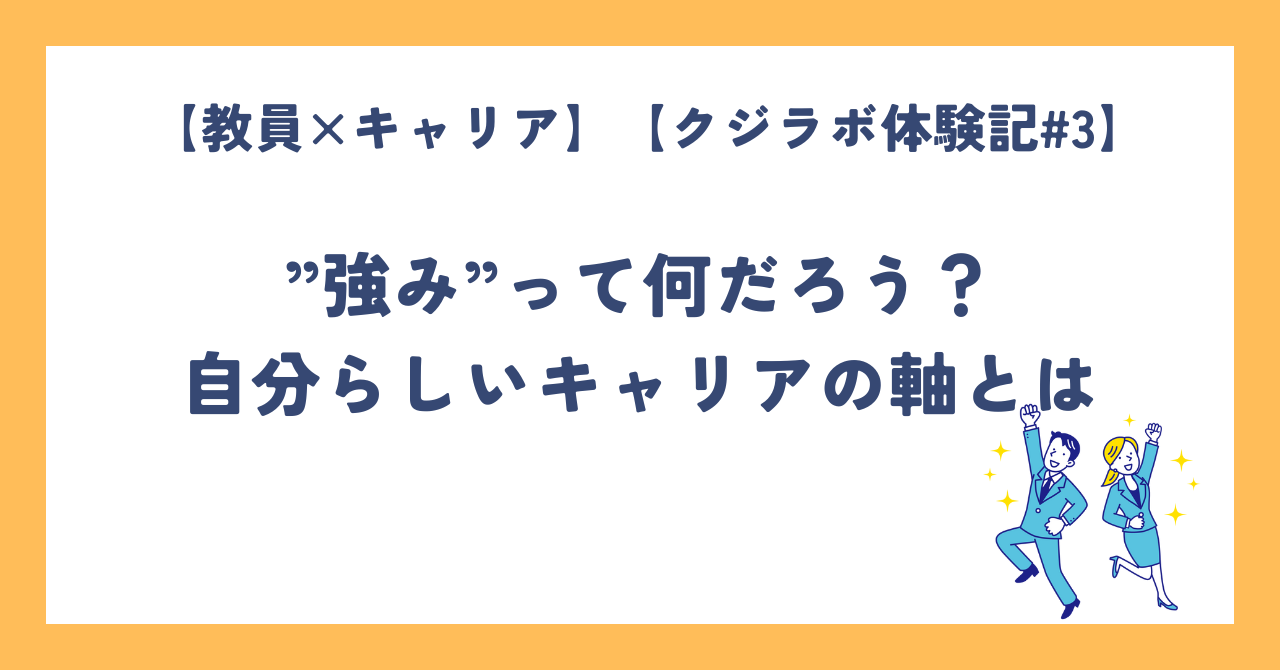

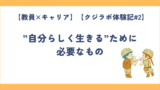

コメント